10月17日、またもや首相は靖国に参拝した。ついで100名を超える国会議員が衆をたのんでであるかのように群をなして参拝を行った。記者が小泉チルドレンの一人に感想を聞くと、中国などの抗議は内政干渉だと、たどたどしく答えた。マニュアルにあるのかもしれない。
たとえ他国に実害を与えない象徴的行為であっても、それが他国の国民感情をいちじるしく傷つけるものであれば、その他国が抗議するのは当たり前である。ぴったりしたたとえではないが、彼の地で国旗が公然と焼き棄てられたら、どの国でも抗議するだろう。この焼き棄てが憲法のうたう思想・良心の自由な表現だと言っても、それは被害国には通用しないだろう。
しばしば指摘されているように、そして最近浅井の「私の視点」(http://blog.goo.ne.jp/asaikuniomi_graffiti/)も述べているように、首相や議員の靖国参拝の背後には中国や韓国への蔑視の感情が潜んでいると、拙者も思う。同様の摩擦がたとえばアメリカとのあいだで起こり、アメリカから抗議を受けたとしたらどうなるだろうか。たちまちヘナヘナとなって以後自粛するに違いない。いや、そもそもそのような摩擦を最初から回避するだろう。だから拙者には、外国から抗議を受けたからといって参拝を取りやめるのはよくないという国民の一部の参拝擁護論も、同じ蔑視感情に支えられているように思える。
中国や韓国が首相の靖国参拝に反発するのは、それがこれらの国への日本の蔑視(とまではゆかなくても軽視)が十分に反省されていないことの象徴的表現であると受け取られるからである。この軽視がそれらの国への侵略の源流にあり、かつ侵略はその軽視を持続・強化させたのだ。この軽視と侵略の事実を日本国民を代表する日本政府がはっきり認め、謝罪する気持ちになった時、靖国参拝はおのずから取りやめになるだろう。
首相は靖国参拝する心情はいずれ理解してもらえる、といつも言っている。だがそれは10年先、20年先になるかもしれない、とも言っている。ここには首相の変わらぬポリティックスが表れている。同じ言行を何度も繰り返し、その言行のめざすものを既成事実にしてしまおうとする策戦である。たとえば靖国参拝を何度も繰り返してゆくと、それが争われるべき問題ではなくなり、次の問題を論じる前提となってしまう。つまり、靖国参拝は内外の両方にとって、問題ではなく「自然」の一部となることを狙っているのだ。習慣化してしまい、「それはそういうものなのだ」と内外に認めさせることが狙いなのである。
しかし中国や韓国にとって靖国参拝は「それはそういうものだ」と、習慣として認める日が時の流れでいつかやってくるのだろうか。もしそれがかりに10年先、20年先にやってくるとしても、日本の両国との摩擦はその間にいろいろの副産物をもたらし、国益を損なうことになるだろう。
首相が替わっても靖国参拝が続く限り、それは中国や韓国への軽視が依然として続いていることのしるしとして受け取られるだろう。たとえその時々の首相が、意識の表層においてはそうした軽視はない、と思っていても、である。(2005/10/21)

|
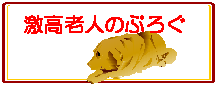
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。