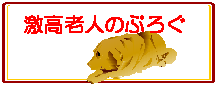「日本近代文学に見られる自我の放棄 ─ 伊藤整の枠組に従って」作田啓一
今日、自我の評価をめぐり意見が分かれているが、この観点から伊藤整の昭和20年代の仕事である私小説論が検討されている。彼は西洋風の発想法による本格小説を高く評価する一方、日本風のそれによる私小説にも強い共感を示す。(400字×60枚程度)
「『死霊』の考究(1)」安部浩
難解をもって知られる埴谷雄高の長大作を「心中から心中へ」の物語として読み解く試み。第一章の本稿では、主人公の兄と彼の昔の恋人、そして彼の革命運動の同志をめぐって生じた心中事件の含意を、3者の視点から探る。(400字×45枚程度)
「ウェイクフィールドの近くて遠い旅」西山けい子
ホーソーンの初期の短編に、格別の動機もなく家出して、妻の動静を20年以上も近くから観察し続けた奇妙な男の物語がある。彼は突然帰宅し、以後平凡に過ごす。いくつかの動機解釈の紹介のあと、著者はそれを「虚無を経験したいという人間の深層の願望」の中に見いだす。(400字×40枚程度)
「E.A.ポーと二つのテレパシーの交錯 ─ 二人のジャックによせて(2)」平田知久
前稿で詳説したラカンによる「盗まれた手紙」の読解へのデリダの批判(「真理の配達人」での議論)をたどる。コミュニケーションの不可能性がそれの成立を支えるというパラドクスに着目したデリダは、不可能性の中で生じる偶然の出会いに、テレパシーの本態を見る。(400字×55枚程度)

|
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。