総選挙で自民が衆院定数の6割を占める結果が出た。しかし党派別得票数では、小選挙区の自民の得票は半数以下である。結果の圧勝は一つには自民が公明と組んで相打ちを避けたことによる。一方、民主党をはじめすべての野党は相当数の票を得ながら死票がおびただしく、それが自民の圧勝をもたらした。それはたとえば民主が8本の安打を打ちながら、わずか2本を上回った10安打の自民が4対1で勝ったようなものだ。
勝ちは勝ちだと言う人もいる。しかし得票総数から見ると、この勝ちがただちに民意を表しているとは言い難い。むしろこの大勝は自民党執行部の選挙戦略の勝利であった。その戦略は選挙の土俵を郵政民営化に賛成か反対かの選択という枠に設定したところから始まり、自公が連携して全選挙区に1人の郵政法案賛成の候補者を立てた計算にいたる。マスコミはこぞってこの土俵設定の巧みさに感心し、民主党がそれへの対抗策を打ち出せなかった無策をばかにした。しかし政局はゲームではないのだ。4対1で勝ったゲームの監督に感心ばかりしてはおられないはずだ。
総選挙の結果を見て、郵政法案の採決で欠席・棄権・反対した自民党参院議員は、特別国会で法案が再提出されればその時は賛成するという意向を続々と表明し始めた。こぞって「民意を尊重する」ためだと言う。だがこれは口実であるとしか思えない。郵政法案を支持していると解される票数は総得票数の半分にも満たないからである。しかもこの票数は、実際には国庫に負担をかけていない公社の職員を民間に移し公務員の数を減らすことが即、国の経費削減につながるかのように訴えた詐術まがいに、かなりの有権者が引っかかったせいもあるようだ。単純なキャッチフレーズの繰り返しが見事な策略だったとマスコミは称賛したが、それは、何度も繰り返せば嘘も本当になると語ったヒトラーの策略とたいした隔たりはない。それは昔ながらのプロパガンダの技法なのだ。
寝返り第一号の鴻池議員はテレビの番組で原口民主党議員に向かい、敗北を素直に認めたらどうだ、などと偉そうに勧告している。民主党の影の内閣で郵政改革担当の大臣に擬せられた原口議員は、その番組では負け組の代表者とされ防戦に追われていた。もっともこの人は小泉首相が日中首脳会談で村山発言を継承すると演説している最中に、自民党議員と一緒になって(総勢80名)、靖国に参拝している。
小泉内閣が発足して以来、国民の上位と下位(中位を除く)との所得格差は確かそれ以前の2倍となっている。負け組をふやしつづけるこの内閣を支持した今回の有権者の大多数は、負け組予備軍ともいえる人たちである。勝ち組を応援して負け組はさらに痛い目にあうだけなのに、負け組はそれでも勝ち組への支持を続けるのだろうか。(2005/9/21)

|
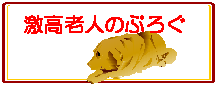
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。