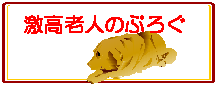「脱植民地化と故郷喪失 ─ ピエ・ノワールとしてのカミュ」 松浦雄介
アルジェリアの脱植民地化は、入植フランス人の当地からの引揚げ ─ 故郷喪失と彷徨 ─ を余儀なくする。カミュの後期小説に、彼ら引揚げ者たち(ピエ・ノワール)の運命の予見を読み取る。(400字×60枚程度)
「究極の他者について」 作田啓一
究極の他者は、象徴化から洩れ落ちた現実界に根をおろす。脆弱者、逸脱者、神秘家など。これらのイメージはアガンベンやドゥルーズ−ガタリの枠組の中にも対応物をもつ。(400字×35枚程度)
「個人から超個人へ ─ 夏目漱石に見る個人主義の問題」 亀山佳明
講演で個人主義の倫理を説いた漱石は同時に『こころ』ではその困難を描いた。この矛盾を超える超個人の思想を、論者は晩年の『明暗』などで探求している。(400字×35枚程度)
「贈与行為についての行為論的分析(1)」 高橋由典
合目的の交換に回収されない「過剰な贈与」の動機は何か。まず、贈与を交換から切り離す思考方法=行為論的還元の手続きを提示する。(400字×30枚程度)
◆◆◆映画散策
『キッチン・ストーリー』『ジョゼと虎と魚たち』『まぼろし』『リトル・チュン』『サンタ・サングレ』
(400字×50枚程度)

|
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。