北オセチア共和国で起きた武装勢力による学校占拠(9月1日〜3日)は、数百名を超える子供たちの死をもたらしたことで世界に衝撃を与えた。人質の大半が子供たちであったことに、これまで国際権力に抵抗する武装勢力にある程度理解を示してきた人たちにも、今回の彼らの行動は絶対に許し難いものとして受け取られたことだろう。子供を犠牲にしてはならないという暗黙のルールが乗り越えられてしまったからである。こうなればもう何でもありだ。どんなに恐ろしいことも起こりうるのだ。
これまで国家権力やそれに匹敵する権力は、その組織性や新しい武器の使用により、許容されうる暴力の一線を次ぎ次ぎに乗り越えてきた。ナチスのユダヤ人狩り、アメリカの原爆投下、クメール・ルージュの大量虐殺。これに対して権力に抵抗する側は、暴力装置が貧弱であるために、そしてまたそれ以上に、彼らがめざす正義がその実現手段に制約を課してくるために、最後の一線を越えることはなかった。自爆は確かにある線を越える手段であった。しかしもともとフランス革命の頃からテロリストは要人を狙うため死を覚悟していたので、自分の命を引き換えにするという意味では自爆は新しい手段ではなかった。今回の学校占拠事件は多数の子供を標的に選んだ点で、最後の一線を越えてしまったという感を与えた。
しかしこの事件にはまだ明らかにされていない部分が多い。武装勢力側は子供たちを人質に取りながら、最初から交渉に応じる姿勢がなかった、という報道が流れた。しかし交渉するつもりがなければ、人質は不要であり、始業式が行われている運動場で銃を乱射すれば、それで十分であったはずである。人質を取ったからには、その解放と引き換えに何らかの要求を持ち出したに違いない。実際、武装勢力側はチェチェンからのロシア軍撤退とイングーシ共和国で拘束されているチェチェン独立派メンバーの解放を要求したようである(毎日新聞社9月3日報道など)。しかしこの要求は拒否されたらしく、2日目から武装勢力側の人質への待遇は一変した。1日目には人質はトイレにゆくことも水を飲みにゆくこともできた。2日目からはこれらも禁止された。状況がこのようなものであったとすれば、武装勢力側に要求がなかったのではなく、1日目に交渉が決裂したあとから、人質もろとも破滅へ向かう行動が始まったのだ。
プーチンは交渉に応じる相手ではないことはだいたい予想できたはずだから、武装勢力はハナから破滅をめざしていたのだ、という見方もあるだろう。しかし子供を楯に取れば、さすがのプーチンも世論を気にして譲歩するかもしれないという、ある程度の期待をいだいていたとも思える。だとすれば、彼らの行動は子供たちを狙ったテロそのものを目的としたテロであるとは言えないだろう。その点では、ただ子供たちを殺すことだけをめざし、社会への怨みを晴らそうとした宅間死刑囚の暴力、文字通り一線を越えるための暴力と、武装勢力の暴力とは同質でないことは明らかだ。しかし子供たちに大量の犠牲が出る可能性が十分にあった点で、武装勢力の学校占拠計画は、やはり一線を越えた暴力を最初からはらんでいたと言われても仕方がないだろう。
しかしそれにしても、人命尊重を第一に考えて解決をめざすとのプーチンの当初の発言はどこへいったのか。本当にその気があったのか。ロシアの国益だけを考えてチェチェンの実質的な独立の要求をひたすら強権をもって抑え込むだけのこの人のポリシーは、場所を選ばない過激な暴力を次ぎ次ぎに生み出すだけだろう。ロシアからの輸出用の天然ガスや石油のパイプラインの安全を保つこと、またチェチェン領土内に埋蔵されている天然資源を支配下に置くことが(浅井久仁臣氏のホームページ「私の視点」)、ロシアの国益にとってさしあたりどんなに重要であると見えようとも、ロシアは弱小民族との共存の道を採るべきだ。たとえばシベリアの天然資源の開発によって、チェチェンの解放で失うものを取り戻すことはできないのだろうか。国連が大国のエゴイズムを抑える力をもっていない今日、大国の自己抑制以外には、せっぱつまった弱小民族のテロリズムと呼ばれる抵抗を根絶することはできないだろう。(2004/9/11)

|
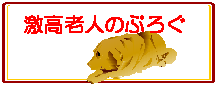
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。