石油については、2003年6月4日に報道されたとおり(英ガーディアン紙)、P.ウォルフォヴィッツ国防副長官は大量破壊兵器問題を戦争に対する「官僚的な」言い訳であるとして斥けたのみならず、あけすけに石油が真の動機なのだと認めてすらいる。「物事をシンプルに見てみましょう。北朝鮮とイラクのもっとも大きなちがいは、経済的に言ってもちろんわれわれはイラクを選ぶということなのです。あそこは石油の大海を遊泳している国なのですから」と。もちろん石油だけではない。アメリカの安全を確保するための世界新秩序を立ち上げるにあたっての要(かなめ)の位置にイラクは置かれていたのだ、という副長官の言葉をこの記事は伝えている(ジジェク『イラク』)。
戦争の大義とはとても呼べないような超大国の国益が戦争の動機であったことを、政府高官が臆面もなく語るところに、日本の政府とのちがいが目立つ。この記事が出てまもない6月11日の党首討論で、共産党の志位委員長が首相に、あなたはまだイラクに大量破壊兵器が隠されていると思っているのか、と追及した時、首相はいまや周知の名言(?)をもって答えた。「フセイン大統領もいまだに見つかっていない。だからといってイラクにフセインが存在しなかったと言えますか? 大量破壊兵器が見つからないといってそれがなかったとは言えない」。こういう軽口が咄嗟に出てくるのが首相の特徴だが、大量破壊兵器は戦争の口実にすぎなかった、などとはオクビにも出さない。首相としては言いにくいかもしれないが、彼だけではなく政府高官の誰もがこの公然の秘密に関しては堅く口を閉ざしていたし、今もそうである。ウォルフォヴィッツ氏なら、彼らを「官僚的」と評するだろうが、彼らにしてみれば、同盟国の政府に対してひたすら律義にふるまっているのだ。
この6月、米シーアイランドでのサミット開会直前に、国連安保理によるイラク新決議(イラクへの「主権移譲」と多国籍軍の駐留を認めた決議)採択が報道された際、首相はブッシュに「米国の大義の勝利だ」と言い、多国籍軍への参加を申し出た。しかしこの新決議に加わった国連安保理の国々は、別にアメリカの「大義」を認めたわけではない。イラクの復興に当たって、アメリカが権利請求に関し一定の譲歩を示したので、これらの国々が妥協したまでのことだ。それだけのことだのに、日本の首相は「米国の大義の勝利だ」などと、恥ずかしくて鳥肌が立つようなセリフを言ってのけた。戦争に「大義」があったことをアメリカ政府以上に認めたかったのだ。「長いものには巻かれろ。そうすれば損はしない」というのが、首相たちのホンネであると、拙者はかねがね思っている。そうである以上、戦争の「大義」など、本当は彼らにとってどうでもよいのだ。だがこのホンネをどこまでも隠し通し、タテマエで押し通すのが彼ら「官僚」のやり口なのである。
もしリベラル・デモクラシーを大中東地域に広めるというのが戦争の「大義」であったなら、この戦争がたとえ民族自決の原則を脅かすものであっても、それなりに承認されうる面があったことだろう。だがネオコンのイデオロギーによって動かされているアメリカ政府にとって、リベラル・デモクラシーの汎化など、一つの口実にすぎないのだ。その点については自由民主党(リベラル・デモクラティック・パーティ)と名乗る政党を背景にした日本の政府も同じことである。リベラル・デモクラシーの汎化など彼らには、どうでもよいのだ。彼らにとって「大義」が何であろうと、アメリカの膨張してゆく国益のおこぼれにあずかることだけが問題なのである。(2004/7/10)

|
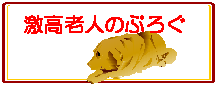
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。