アメリカの民間人(と言っても普通の民間人ではなさそうだが)四人の殺害に端を発したファルージャでの戦争犯罪を思わせる惨劇が報道される中で、我が日本では国会議員や閣僚などの年金未納・未加入が次々に明らかにされ、大騒ぎとなっている。呑気な話だ。でもやはり、自民党だけが、未納・未加入者を党として公表しないとなると、未納・未加入などたいしたことはないと思っている拙者でさえ、やじ馬的関心が出てきて、あの人はどうかな、と思ったりしている。
5月1日、安倍幹事長はワシントンで記者団に次のように語っている。「保険料を払っていない人は(その分は)もらえない。年金財政上も、その人には出さないからロスにはならない。報道の仕方がおかしい。犯罪・脱税ではない」。確かに犯罪ではないが、年金を一般の自由加入の保険と同一視する発言は年金法案を提出しようとしている与党の幹事長としては、明らかに失言である。年金は自分のためだけに納めるのではない。年金制度を支えるために納めるのだ。年金納入はその意味では税金納入に近い。幹事長がこんなふうなのだから、自民党から未納・未加入の人が続出しても不思議ではない。ところで、その発表は個人まかせと言われてしまうと、黙っている人、あるいは納めてはいないが納めていると思っている人は、そのままで済んでしまいそうだ。
だから、と言うわけではないが、やはり気になる人がいる。小泉首相はどうなんだろう。厚生大臣をしていた時なんか、人ごとながら心配だ。本人は完納しています、と言っている。しかしそう言った人があとになって「じつは・・・」と告白した例もあるから気がかりだ。今のところ、この気がかりをはっきり口にするマスコミも出てこないのが不思議なくらいである。
ついでに付け加えると、公明党の代表と幹事長が未納を発表したのはよいが、自分で自分を譴責する処分だけで済まそうとしていることも心配だ。冬柴幹事長は職を辞さないのは「適正」だ、と胸を張った。あとになって自己譴責だけでは軽過ぎると各所から批判が起こり、「適正」な判断を取り消す始末になりはしないか、と心配している。(2004/5/14)
午後5時20分ごろ、テレビ画面のテロップで「小泉首相年金未納」のニュースが流れた。やっぱり。心配していたとおりだった。クックックッ。
のちのニュースで小泉首相は、未加入の期間は義務化以前のことであり、義務化以後は全部払っている、と言っていた。ホント?

|
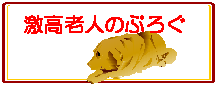
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。