イラクで人質になった3人とその家族に対するバッシングは異様だった。学級内での凄惨ないじめが国民的規模で展開されたかのようであった。これに参加したのはいじめっ子に相当する一部国民の権威主義者たちだけではなく、教師に相当するグループもそれに加わった。というよりも、このグループである政府与党と一部マスコミの連合軍の主導のもとで、いじめっ子である権威主義者たちが操作された、と見たほうが事実に近いかもしれない。
3人が人質になったという情報が伝えられた段階では、国民は「かわいそう」というふつうの反応を示した。その中の一部が人質とその家族への攻撃に転じたのは、家族が人質の解放のために自衛隊を撤退させてほしい、と訴えた時からである。この訴えが政府与党の逆鱗に触れ、一部マスコミを媒介として権威主義者たちの攻撃性をあおったのだ。もし家族が人質解放のためアメリカ軍の援助を訴えたとしたら、政府与党はニンマリしたことだろう。だが誘拐集団がアメリカに敵対していることを知っている家族が、そんなことを訴えるはずがない。一般に、警察に知らせれば人質の命はないぞと脅されている家族が、まず思いつくのは身代金の支払いであって、警察に知らせることではない。だから3人の人質家族は、身代金を要求されれば、まずその要求に応じるかどうかをまっ先に考えるだろう。だが身代金の要求はなく、それに代わるものが自衛隊の撤退であったので、それを政府に訴えたのは、こういう状況に置かれた家族のふつうの反応の範囲内にある。ところがふつうの誘拐の場合とは異なった特殊な状況のもとに置かれているために、家族のこの反応が、政府にお願いしているのに反政府的な要求を突きつけている、と取られてしまって、「いったい何様のつもりだ」という憤激をもたらしたのだ。それはお上(かみ)にたてつくのはけしからんという憤激であり、いつもお上と自分を同一視している権威主義者たちの超自我の憤激なのである。
この憤激を刺激し、そのうえでそれに便乗する政府は、人質事件に有効に対処しえなかった(ように見えるのだが)自分たちの弱味を隠そうとして「自己責任」という奇妙な理屈を持ち出し、それに与党や一部マスコミが同調した。人質たちは政府の警告を無視して危険な場所へいったのだから、解放にいたるまでの費用は人質が支払えという理屈である。国民の血税をつぎ込ませた責任は人質にある、というわけだ。一部マスコミが計算したこの費用はだんだんつり上がって、30億円にまで達している。この中には、各所に連絡を取るために時間外の勤務をした外務省職員の超過勤務手当も含まれている。超過勤務を禁じている役所もあり(したがって時間を超えて働いても超過勤務手当は出ない)、時間を超えて働いてもただ働きがふつうの民間企業もあるというのに、である。そしてもちろん、アッパークラスでアンマンに飛び、高級ホテルのスイートルームで事務を執ったという逢沢副大臣ご一行の使った経費も含まれる。逢沢氏は人柄がよいために福田官房長官に叱られたりしているので憎めないが、しかし大金を使った割りには、人質救出にはこのご一行はあまり役立つ働きはしなかったようだ。それはともあれ、こうした非常事態に備えて予算は計上されているはずである。そしてそもそも、時の政府の方針に反する行為をした邦人がいたとしても、その邦人を救出するのが政府の義務なのだ。人質に金を返せというのは、十分に救出の責任を果たしたとは言い難い政府の弱みを取りつくろうための人質への責任転嫁である。そんなに金の問題を持ち出すなら、たとえば公明党の代表が、サマーワを数時間「視察」しただけで、ここは安全と報告した際の渡航費用は無駄遣いではないか(それともこの費用は公明党もちだったのだろうか)。数時間で何が分かるというのか。この党の幹事長は、自己責任だ、人質は金を払え、と記者団に公言していた。この人は何様のつもりなのだろう。一部マスコミの側では、例によって人質とその家族の過去をほじくり返し、あやふやな情報を流すことで彼らのプライバシーを侵害している。まるで犯罪者扱いだ。
いったい彼らが何をしたというのだ。人道支援のために、あるいは弱者である被占領者の側の実態を世界に知らすために、イラクに入ろうとしただけではないのか。危険性を告げたはずだと政府は言うが、その危険性が何%かが予測できないのが、危険性の情報である。政府とNGOとの連絡が十分とは言えない状況のもとで、危険率が50%を越えるという警告が出れば別だが、今回の場合の警告はそれほどはっきりしたものではなかった。かりに彼らの入国は大胆過ぎたと言える部分があったとしても、だからといって彼らが犯罪者扱いされる理由にはならない。むしろ彼らは、閉鎖的で自分たちの安全だけしか考えないのが日本国民だとされていたのに、国家の枠を越えて人道のために動く日本人もいる、ということを、世界に示す功績があったのだ。それなのに日本へ帰ると犯罪者扱いである。日本のこの権威主義的文化の恐ろしさを人質とその家族は甘く見ていたかもしれないが、それは彼らの罪ではない。ところで政府は一段グレードの高いイラク入国への警告を考えているそうだが、その際「サマーワは除く」と注記するのだろうか。
あとで誘拐された2人は、拘留期間も短かったし、自衛隊を撤退せよという誘拐者側の声明もなかったので、初めの3人とは事情が違っていた。それに3人と2人とのあいだにはアマとプロの違いもあるようだった。あとの2人は3人のように打ちしおれたりしておらず、そのうちの1人は「日本人であるという理由だけで捕らわれたのだ」と昂然と発言した。この強さを前にして、「いじめの共同戦線」も今のところは十分な反撃をしかねているようだ。だからといって、事情を異にする先の3人とその家族の弱さを云々することはできない。それほど彼らへのいじめは残酷だったのだから。こんなことがあっていいのか。(2004/4/23)

|
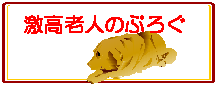
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。