公明党の神崎代表らが中国を訪問した際、中国共産党対外連絡部の劉洪才副部長との会談で劉氏が、日独仏3ヵ国で受注を争う北京−上海間の高速鉄道計画について、小泉首相の靖国神社参拝問題を理由に、中国が日本を選択することは難しいとの見方を示していたことがわかった(『朝日新聞』大阪版、2月17日)。もしそれが理由で日本が外される事態が起これば、首相の靖国参拝はかなりの国益の損失を招いたことになるだろう。実際にその通りになるかどうかはわからないが、中国が日本の巨大市場となっている今日、この鉄道計画以外の面でも、首相の行動は日本の産業界にマイナスの影響をどこかでもたらす可能性をはらんでいる。国益を尊重すると言い続けている首相は、この点についてどう考えているのだろうか。
首相は平和を祈願するために戦争の犠牲者を悼む自分の心情は、いつかは外国の人々にもわかってもらえるはず、と繰り返し言ってきた。しかし靖国には平和を破壊したA級戦犯が合祀されている。靖国には、侵略戦争の意思決定に参加した人々と、彼らによって戦争に巻き込まれ、何の罪もなく死んでいった人々とが共に祀られているのだ。加害者と被害者とが共に祀られていることが、日本の侵略により多くの犠牲者を出した外国の人たちにとって問題なのである。彼らは同じく戦争の犠牲となった無名の日本人たちを悼む行為に異議を申し立てているわけではない。A級戦犯を祀っている神社への参拝が問題なのだ。
首相は、A級戦犯も極東軍事法廷で死刑宣告を受けたのだから、やはり戦争の犠牲者であることには変わりはない、と考えているのだろうか。確かに政治のレベルを超えた高い宗教的レベルに立てば、加害者と被害者の区別はないだろう。死者はすべて神か仏になる(しかしその場合には、外国人の死者−たとえばBC級戦争犯罪の犠牲になって死んだ外国人の捕虜−も祭祀の対象になるだろう)。しかし現実の政治のレベルではそうはいかないのだ。
何の大義もなしに、自国の利益を追求するため土足で外国の領土に踏み込み、民衆が虐殺と略奪の大きな被害を受けた時、その外国が、侵略の意思決定を行った日本のかつての指導者たちを祀ってある神社に、この国の代表者が参拝することに嫌悪感をいだくのは当然である。首相がその外国に向かって、自分の心情がいつかわかってもらえるなどと期待するのは厚顔に過ぎる。自分こそ侵略戦争の犠牲になった国の人々の心情を理解すべきなのだ。その外国の非難に対して、首相は外国の指図は受けない、などと強がって見せ、偏狭なナショナリストぶりを発揮して一部の国民のウケを狙っているようだが、問題はその「指図」の内容なのだ。たとえ外国からの要求であっても正しい要求であれば従うべきである。
確かに、極東軍事法廷は勝者が敗者を裁いたのだから、この法廷そのものが法理に適わない、という指摘は古くからある。しかしだからといって、侵略戦争を引き起こした指導者とその戦争によって犠牲になった国内の人々とが同等の責任を負うことにはならないだろう。あるいは公平な裁判が行われていたら、日本の指導者は戦犯とされることはなかっただろうと考える人もいるようだが、たとえドイツのように国際法廷とは別に自国の法廷で裁判が行われたとしても、指導者とその他の犠牲者との区別は残ると拙者は思う。先に書いたように、高いレベルでは戦争に関しての加害者と被害者の区別はない。しかし現実的な政治のレベルではそうはならない。たとえば小泉氏が一宗教者として靖国に参拝しても、外国は何ら非難しないだろう。だが小泉氏はいつも首相の資格での参拝にこだわっているのである。
もっとも、1978年に行われたA級戦犯合祀以前から、靖国は侵略戦争へと国民を誘導する日本の軍国主義の装置として機能していた、との内外の認識があった。それゆえ1975年にイギリスのエリザベス女王が来日した際にも靖国への表敬は回避された。無名戦没者のための千鳥ヶ淵墓苑を訪れる案もあったが、これは靖国側の反対で阻まれた。A級戦犯の合祀が加わり、靖国と侵略戦争との結びつきのイメージは一層強化されたのである。外国の要人が足を向けることのできない戦死者を祀る施設がそのままの形で温存され、外国の目を気にしながらも(そのために8月15日が外されている)そこへの参拝を強行する首相の国際社会への感覚はどうなっているのか。あのタカ派の中曽根氏でさえA級戦犯の分祀を真剣に考えているのに、この超タカ派の首相の鈍感さは公平に見て度を超している。そしてこの鈍感さが国益の損失を招きかねない事態にまで立ちいたっているのである。(2004/2/21)

|
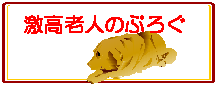
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。