戦後から数年のあいだ、教師が理想の国はどこかと尋ねると、スイスと答える小学生が多かった。スイスは戦争に参加しない国として知られていたからだ。今でもスイスはそうである。だがスイスをモデルとする日本人は少なくなった。
スイスと言うと、キャロル・リード監督の『第三の男』の中で主人公を演じるオーソン・ウェルズが、平和国家であるスイスのことを、「時計を作ることくらいしかできない国」と揶揄していたことを想い出す。貧しい国ではないが、繁栄はしていない。国民は概してまじめだが、陰気で人づき合いはよくない。世界の中ではあまりパッとしない国ということになっている。こうした実態が知られるにつれて、スイスに憧れる日本人が減ってきたのも、一種の「自然」の成りゆきであろう。だが、もし日本人が平和国家を望むなら、今日の国際状況においてほかに適当なモデルはないのだ。平和国家であろうとすれば、人は国家に多くを望んではならない。確かに、ヨーロッパと北東アジアとでは国際的環境が違う。それにしても日本が北東アジアの平和国家となりうる可能性は残っている。
日本の為政者たちは、「国際社会」の平和のために自衛隊を動員しないで自己保存だけを求めるのは許されない、と言う。彼らの論理に従えば、「国際社会」(じつはアメリカ中心の有志連合)との「つき合い」を軽んじて、独り引きこもるのは虫がよすぎる、というわけだ。しかしこの引きこもりは彼らが言うほど楽な方向の選択ではない。「つき合い」のほうがむしろ楽を求めての選択なのだ。部分的にしか当てはまらない譬えだが、学級のリーダーであるいじめっ子に同調しないほうが、いじめに加担することよりもずっと勇気が要る。それに加担しないといじめっ子に冷遇されるという苦しい結果を招きかねないからだ。
確かに、いじめられっ子は悪い環境に育ったためにひねくれていることもある。それが国家である場合には、国内で人権侵害を行っていることもある。しかしそれでも、平和国家はこの非人道的な面をもつ国家を武力で攻撃することに加担してはならないのだ。平和国家は正義を求めはするが、武力による制裁への加担を禁欲しなければならない。これもまた平和国家に要求される辛い我慢なのだ。平和国家としての存立は決して楽な道ではない。しかしその道を選ぶことは、究極においては地球上に戦争をなくする1つの段階であると言えるのではないか。
平和国家はみずからの防衛を放棄するわけではない。防衛放棄は個人の場合も困難だが、国家の場合はさらに困難だ。しかし防衛の範囲をぎりぎりのところまで縮小することはできる。かつての日本は満州をもって生命線であるとした。しかしそれは植民地の拡大であると外国からみなされ、戦争のきっかけとなった。平和国家にとっても防衛は必要だが、それは他国民を犠牲にする「防衛」であってはならない。(2004/1/17)

|
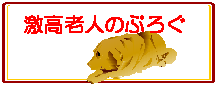
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。