今年は政治家の失言が目立った。その多さにおいて目立っただけではない。そのあと謝罪もしないことでも目立った。以前はタテマエ上謝罪することが多かったが、今年はホンネを言って何が悪いとばかり、失言を取り消さない場合が多かった。からだをゆさぶって歩く或る現閣僚は、かつての朝鮮人の創氏改名は、彼らが望んだものであり、強制によるものではない、と言い放った。たとえそうであるとしても、そうしなければ生活しにくい状況に置かれたためなのだから、自発性よりも強制力が上回っていたことは確かだ。この現閣僚は自分を強い日本国家と同一化しており、その支配の正当性をみじんも疑っていない。
もう一人の閣僚(当時)は、殺人を犯した少年の親は「市中引き回しの上打ち首」に値すると放言した。この人も反省することなく、逆にこの発言を支持する沢山のファックスが集まっていることを自慢していた。しかし新聞の投稿欄に、子供を殺人者にしようとして育てた親などいるはずはないから、この発言は酷だという批判が出た。拙者もその通りだと思う。この元閣僚は、被害者の遺族の身になって発言したのだから、その点は納得できるという意見もあったが、拙者は十分には納得しかねる。そういう要素がないとも思えないが、この人の怒りの来たる出所は、自分がそれに拠りかかり、それを利用して今の地位を獲得してきた秩序への侵害である。確かに、それを侵害したのは少年であってその親ではない。だがさすがに少年を攻撃するわけにはゆかないから、その親に怒りが向けられるのだ。しかしどんな秩序にもほころびがある。そしてそのほころびを少年の親といった特定の個人に帰し、彼らの迫害を望むところまで進む論理はほとんど暴力的だ。こうした少年非行をもたらした責任の何パーセントかは政治にあるといった考えは、この元閣僚の頭を一瞬たりともよぎったことはなかったのだろう。
二人の閣僚の発言には共通点がある。それは自分が同一化している国家や秩序に少しでも傷があることが指摘されたり、明らかにされたりすると、怒りをもって反応する点だ。彼らは国家や秩序に同一化しているから、それらが傷つくと自分が傷つくのと同じ防衛の反作用を起こすのである。そんなに同一化しなくてもよろしいのではありませんか。だから拙者はナショナリスティックな昂揚や道徳的憤慨が嫌いなのだ。しかしこういった人物を閣僚にまでのし上がらせた政党の組織が問題であり、そしてこの種の政党を第一党にした我々国民も責任なしとは言えないだろう。(2003/12/28)

|
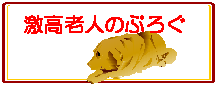
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。