真向かいの席に男が大股を開いて坐っている。結構混んでいるのに、二人分のスペースを占めている。拙者はもっていた傘の先で男の股間を突いてやりたい誘惑に駆られる。日本の男性にはどうして大股開きが多いのか。外国の国際空港のロビーで大股開きを見かければ、日本人男性と推定してほぼ間違いない。
どうして大股を広げるのか。あぐらをかく習慣からきているのか。そうでもなさそうだ。威張って見せるためか。そうらしい。だが大股開きはどうして威張って見えるのか。大股開きは無防備のしるしであるようだ。俺は強いから急所をさらしても平気だ、と言わんばかりである。日本が男性にとって長いあいだ平和な国だったために、こういう習慣が続いているのかもしれない。若い世代が次々に出てくればこの習慣は変わるだろうと思っていたが、あい変わらず高校生にも威張って股を開いている者が多い。
スポーツ選手のあいだでは大股開きが普通のようだ。長嶋茂雄さんは例外で両膝をそろえている。この人の能天気ぶりにはあまり好感はもてないが、大股を開かない点で気に入っている。威張りと大股開きの関係を見事に実証しているのは阪神OBの川藤さんである。
一方女性に関しては、おばさん世代の通路側坐りが目立つ。二人掛けあるいは四人掛けの座席で窓際に坐るのを避ける。混んできても通路側から窓際へ移動することは少ない。通路に立っている人は奥の空席に目をやるが、おばさんの膝による障害を突破するのが面倒なので、立ったままでいる。おばさんのほうは居眠りなんかして知らん顔だ。
通路側坐りの理由はわかりやすい。窓側に坐ると、あとで人が通路側に坐ってくるために、自分が降りる時に面倒になるからだ。しかし遠くまで乗っている人もかなりいる。すぐ降りることを期待して待っている拙者のほうが、先に降りることがよくある。行き先が遠くであっても、通路側坐りが習慣化しているのだ。
ヨーロッパの大都会の住民のほうが、公衆道徳に関しては日本人よりもずっと敏感である。愛国心を養えなどと大きなことを言う前に、識者は目の前の公衆のマナーにもっと注意を向けるべきだ。(2003/10/31)

|
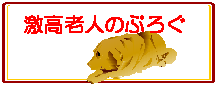
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。