シンキロー前首相はホリエモンが気に入らないようだ。彼は、ホリエモン氏は外国資本から金を借りてニッポン放送を支配しようとしているが、これが成功すると、外国が日本の放送機能に影響を与えることになるから用心しろ、と警告した。そして金のために何でもする人間が出てきたのは、これも教育のせいだろうか、と慨嘆してみせた。この人は発言すると、いつも失言めいてくるので、やめたほうがいいとかねがね思っているのだが、自分のおしゃべりに自己満足するキャラクターらしいので、仕方がないだろう。沢山の放送メディア(強力なNHKを含む)がある中で、一つくらい外国資本の影響を受けるメディアが現れても、それがどうしたというのか。それにまた、その影響がどんな形で出てくるのか全く未知数の段階なのだから、これは不安神経症的な反応ではないか。さらにまた、我が日本国民はあらゆる面で間接的にせよアメリカのメディアにすでにさらされ続けているではないか。
長年にわたり、自民党の主流(プラス高級文部官僚)は東大を頂点とする学歴社会の上で階層制を築き上げるよう教育に干渉してきた。日教組の抵抗を排除することに成功した今日、この教育界の支配は加速している。こうした階層制の梯子をいわば飛び足のようなスピードで駆けのぼってきたホリエモン氏は、教育の失敗例どころかむしろ成功例ではないのか。しかし、と反論する人もいるだろう。いくら金をもうけても、その手段がいかがわしいなら、成功例とは言えないのではないか、と。いかがわしい手段とは何か。それが何であれ権威やしきたりに反する手段である。エライさんたちがホリエモン氏に好感を寄せないのは、氏が非合法ではないとしてもいかがわしい手段を用いているように見えるからなのだろう。このいかがわしさの中には愛国心の欠落(国家の権威の軽視)も含まれているようだ。実際にはホリエモン氏に愛国心が欠如している証拠などどこにもないのだが。
最近、中山文科相もまたあるミーティングで得意のお騒がせ発言を行った(『朝日新聞』大阪版、3/6)。彼によると、競争を悪だとする教育が、競争に耐えられない子供を育て、このために大量の「ニート」やフリーターが出てきた。だから、教育の場で競争の重要性を強調すべきだ、そうでないと、落伍した若者に将来後悔を味わわせることになるだろう。氏によって称揚される競争原理は前述の階層制を支える原理であり、したがって格別新しい主張ではない。それは学校に、塾に、予備校に、そして家庭にもかなり以前から浸透している。ただ、学校には平等主義の価値観がある程度残存しているので、これを真正面から攻撃することを、エライさんたちも多少はためらってきたのだ。この背景のもとで中山氏が蛮勇をふるって発言した点が注目されたのである。しかしこの発言に含まれている事実認識には疑問が生じる。「ニート」が増えてきたのは、競争原理が教え込まれていないためではなくて、今は競争社会であることは分かっていながら、あえて競争から身を引こうとする若者たちが増えてきたためではなかろうか。ならば、競争から身を引こうとする気弱な心性がなぜ広がってきたかという問題の立て方のほうが、事実への対応としては的を射ることになるだろう。
中山発言にもまた、競争の中で生き残るという目的のほかに、手段の適切さの問題が出てくる。この人は、学校現場での国旗掲揚と国歌斉唱に関し、その気にならない先生方も、生徒たちには国旗・国歌に敬意を払うよう教えるべきだ。そうでないと、将来子供がひどい目に遭うだろう、と言う。ここでもまた、権威やしきたりに従うことが、どんな目的を追求するにせよ必要な手段であることが強調されている。
目的にかかわる「進歩的な」競争原理と手段にかかわる「保守的な」権威・しきたりの尊重。この2つが自民党主流の教育観の軸である。ところが、この目的と手段とはいつも完全に両立するとは限らない。ホリエモン氏は両者の矛盾を露呈するような形で舞台に登場してきた。シンキロー氏やその一派である小池環境相は、手段のいかがわしさの面に注意を向けている。一方、麻生総務相は手段面の強調に反発するかのように時間外の株式取得は全く合法の範囲内であると発言している。ホリエモン氏はエライさんたちの教育観を問うことにも一石を投じた。(2005/3/11)

|
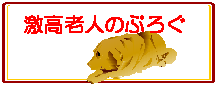
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。