2001年1月30日にNHK教育テレビが放映した従軍慰安婦制度の責任者を問う番組は、放映直前にいたって大幅に改変された。その改変のいきさつを番組制作局のプロデューサーが告発し、この突然の改変はNHK幹部らが一部国会議員の意向を取り入れたためであることが明らかにされた。朝日新聞はそのいきさつを検証するため、これらの幹部や国会議員に対して面談を行い、その取材結果を1月18日の紙上で報道した。それによれば急遽行われた番組内容の大幅な改変は、NHKが政治的圧力に屈したためである。
この報道に対し、当時NHK放送総局長だった松尾武氏(上記幹部らの1人)は19日記者会見を行い、面談に際して「政治的圧力を感じていない」と答えたのに、「内容がねじ曲げられている」と反論した。これに対し朝日新聞は松尾氏が取材した記者に語ったとされる記事には「根拠があり」、氏は「前言を翻した」と抗議している(『朝日新聞』1月20日)。一方、中川昭一経産相は、18日の記事では放送以前にNHK幹部と会ったとされているのに、現時点では放送以後に会ったのだから番組改変とは無関係だ、と語っている。またNHK幹部が会った安倍晋三幹事長代理も、放送前にこの幹部と会ったことは認めているが、改変に向けて圧力をかけた覚えはない、と語っている。
拙者としては、細部はともかくとして、大筋では「政治的圧力を感じた」という朝日新聞の報道は当たっていると思う。それは面会した2人の政治家が「日本の前途と歴史教育を考える若手の議員の会」の有力メンバーであり、その観点からこの番組に不快感を伴った関心を寄せていることを、NHK幹部が面会以前に知っていたからである。そしてまた、この2人が政権政党の中の有力者であり、NHKに関する予算審議などに関して、NHKの経営その他に影響力をもつ人物だとみなされていたからでもあるだろう。安倍氏は番組放送前の1月29日にNHKと会ったのは、向こうから「予算の説明に伺いたい」と言ったから会っただけで、自分から呼びつけたわけではない、と語っている。しかし呼びつけたかどうかはたいした問題ではない。放送直前という切羽つまった時点でお伺いに出向かざるをえないと感じる状況が作られていたのでお伺いにいったので、呼びつけられたのと、そんなに大きな違いはない。その状況とは安倍氏たちがこの番組に不快感をいだいていることがNHK側に伝わっていた、という状況である。安倍氏は出向いてきたNHK幹部に向かい、次のように語ったという。「NHKがとりわけ求められている公正中立の立場で報道すべきだ」。これは特に問題の番組を指しての言及ではなかったかもしれないが、その番組の放映を気にして出向いたNHK幹部がその発言の中に単なる一般論以上のものを聞き取ったとしても不思議ではないだろう。続いて氏は取材にきた記者に対し「国会議員として当然、言うべき意見を言ったと思っている。政治的圧力をかけたこととは違う」と語った。しかし安倍氏は単なる一国会議員ではないのだ。彼は政権政党の有力者なのだ。だからこそ、幹部がお伺いを立てにやってきたのである。こういった状況のもとでは、幹部がNHKは公正中立であるべきだという発言を、政治的圧力と感じても当然である。氏と同じく上記の会の有力メンバーである中川氏も、「番組が偏向している」と圧力をかけていた。氏はNHK幹部と会ったのは、今の時点では番組後と主張している。たとえ番組後であるとしても、すでに番組以前から「偏向している」という氏の意見がNHK側に伝わっていたことは確かだ。
安倍氏は自分たちの意見が「国会議員として当然の意見」であると言うが、あなたたちの意見も「偏っている」と言う国会議員もいるだろう。自分たちの意見を「国会議員として当然の意見」などと主張するのはおかしい。彼らが国会議員を代表するかのようにふるまう権限を誰が与えたのか。彼らは自分たちの特殊な意見を有力者としての立場を利用してNHKに押しつけているのだ。
一方、NHKの松尾武氏は番組の改変は政治的圧力を感じたからではない、と語っている。しかしこの放映直前の改変は、当該番組に対する有力政治家たちの不快感が伝わっていなかったとしたら、行われなかった可能性が強い。ただ、松尾氏の釈明は部分的には真実を語っているようにも思われる。というのは松尾氏ら幹部は、ある段階からこの番組が特定の政治家だけからではなく、他のグループからも攻撃を受けそうだという危惧をいだいていた、と思えるふしがあるからだ。その危惧を感じて番組を編集し直そうという気持ちが、安倍・中川両氏の不快感が明確に伝えられる以前に醸成されていたとしたら、幹部たちは「政治的圧力を感じた」ためではなく、いわば〈自主的〉に改変をめざしたとも言えるだろう。事実、2001年1月19日以降から少しずつ手直しが行われていた。他のグループからの圧力は安倍・中川両氏からのそれと同根のものなのだ。だから幹部たちはこれらの圧力をいわば〈内面化〉し、改変したい気持ちをかなり以前からもっていたので、政治的圧力を取り立てて感じなかったと釈明しても、全面的に虚偽を申し立てているとも言えないのである。
しかしそれにしてもこの会見は、自分の組織内の地位を不安定にすることを覚悟したうえでのプロデューサーの告発を否認せざるをえない帰結をもたらした。彼は上層部から軽挙妄動したという烙印を押されることになった。組織防衛のために政治家に累を及ぼさないよう、自主的に決めたと発表した上層部は、政治家をかばおうとして同僚のプロデューサーを孤立させ、見殺しにした。一方自分たちの地位は安泰なのだ。これら幹部たちの心は痛まないのだろうか。(2005/1/20)

|
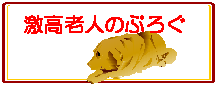
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。