拙者はかねがね日本人の美点は発達した羞恥心にあると考えてきた。ところが、この頃その羞恥心がだんだん衰えつつあるように思えてならない。
羞恥心とは何かという問に対し、いろいろの人がいろいろの答を出している。拙者も一つの答をもっているが、拙者の念頭にある羞恥とはどういうものかを示すために、まず例を挙げてみよう。たけしとたかじんは共に複数のレギュラー番組をもっている。たけしは羞恥心があり、たかじんには羞恥心がない。ダウンタウンの松本には羞恥心があり、浜田には羞恥心がない。たけしやたかじんの番組でしばしば登場するハマコーや橋下(はしもと)弁護士は、羞恥心欠落の代表格である。
羞恥心とは何だろう。それはまず自分の中の内密の部分を外部から遮蔽しようとする心である。その部分の露出を防ごうとする心であると言ってもよい。この内密の部分は人それぞれによって、また状況ごとに様々である。大多数の人々が共有する状況を一つ挙げるとすれば、それは裸であろう。人はたいていの場合、裸を隠す。しかし内密の部分は裸だけではない。人は誰かへの思慕を、苦しかった経験(たとえば戦場での経験)を、何らかの信仰を、人前にさらさないよう防衛する。ではどうして内密の部分を人は遮蔽しようとするのか。内密の部分とはその人に固有の特別の部分である。それが外部にさらされると、それは外部の一部分と化し、変質してしまう。いろいろの個別性があるが、この個別性の喪失は、究極のところ、自分は今こうして生きているという感情の剥奪なのだ。この生命感の凝集している部分が内密の部分なのであり、それゆえに人はこの部分の露出による生命感の剥奪から自分を守ろうとする。これが羞恥心である。内密の部分が外部にさらされる時、自分が今こうして生きているという感情は、生きているという客観的な事実に置きかえられてしまう。それはたとえばカメラの中にあるフィルム上の映像が、光線に当てられるとぼやけてしまうようなものだ。
しかし羞恥心は内密の部分を遮蔽するだけではない。それだけなら、羞恥心は人を内部に閉じ込める働きしかもたない。そうではなく、羞恥心はその内密な部分を外部へ向かって伝達しようとする。それは抑制と共に表現をめざしている。ただしこの表現は外部の視線、主観的感情を客観的事実に置きかえようとする一般化の視線に自分を合わせ、自分を失うための表現ではない。そうであるなら、その表現は表現とは言えないだろう。羞恥心を通しての表現とは、このような一般化にさからって自分の生命感を外部へと広げ、そのことによって生命感をいっそう高めようとする表現なのだ。羞恥心をもつ人の自己表現がそれをもたない人の自己表現に比べて他者を魅きつけるのはそのためである。
むつかしい議論になってしまった。拙者には日本人はその美点である羞恥心をしだいに失いつつあるように見える。芸能界で羞恥心の欠落した人たちが続々と登場してくるのは、その欠落に不快感をいだかない視聴者がふえているからなのだろう。芸能界だけではない。様々な領域で羞恥心の欠落した人々が勢力を増してきているように思える。どうしてこんなことになったのか。この問には簡単に答えられそうにない。そもそもこの問そのものが成り立つかどうかを疑問視する人もいることだろう。そこで今はこの問を提出することだけで終わることにしたい。(2004/12/25)

|
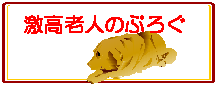
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。