今年もまた暮れに向けて『忠臣蔵』の連続ドラマがテレビで放映されている。戦後以降に限っても、この作品は何度上演・上映されたか、精確に数えることはむつかしいくらいの数だろう。この作品は占領軍政下で一時上演・上映が禁止されたことがあった。武闘ものは軍国主義の再来の刺激となると判断されたからかもしれない。しかし、この作品は強者の倫理に立つ軍国主義とはほど遠い。一般に日本人に定番として親しまれている作品には、強者の倫理に立つものは皆無であると言ってよい。
『忠臣蔵』の魅力についてはいろいろの説があるだろうが、拙者はこの作品にも日本人の判官びいきの心理に訴える魅力が基本にあると思う。吉良上野介の理不尽ないじめに報復しようとした浅野内匠頭は、幕府の公権力により切腹させられる。彼の家臣の有志は城代家老であった大石内蔵助のリーダーシップのもとで吉良邸に押し入り、彼を殺害して主君の怨みをはらす。これがよく知られているストーリーである。大石を含む47人は志を果たせなかった主君の代わりに復讐をめざすが、彼らにはほかに傍役の敵がいる。それは幕府の公権力である。公権力は刃傷の原因となった吉良を全く咎めることなく、浅野に切腹を命じ、領主権さえも剥奪した。47人は吉良に私的復讐を行うことにより、不当な裁定を行った公権力への抗議の意思をも表明したのだ。
きまじめな地方領主の浅野は賄賂などを使って中央の高官吉良のきげんを取り結ぶことができず、意地悪され、かっとなって暴発してしまった。彼は一瞬にして人生の失敗者となったのだ。観客は彼の短慮にいくらか批判的であるとしても、根本的には弱者としての彼に同情する。そしてこのような主君の怨みをはらそうとする忠臣たちの報復行動に応援を惜しまない。公権力に反抗して切腹の刑に処せられた47人の弱者の側に立つのである。
香田さんが囚われの身となっているビデオが流された直後、小泉首相は即座に「自衛隊は撤退しません」と宣言した。すぐそのあと、12月14日までは世論も考慮に入れながら撤退するかどうかを検討すると言っているのだから、「武装勢力を刺激しないような言い方はできなかったのか」という声も上がった。しかし、「ブッシュいのち」のこの人は、即座にいちるの望みを断ち切ったのである。香田さんに軽はずみのところもあっただろうが、国家権力に見放された弱者のこの人に同情する日本人は少なくないだろう。
アラファト議長が亡くなった。強大な軍事力をもち、そのうえ超大国アメリカの支援を受けているイスラエルに対し、パレスチナは余りにも無力だ。その指導者であった議長の死はパレスチナ人にとって大きな痛手である。判官びいきの日本人なら、パレスチナを応援しないわけにはいかないだろう。何者かの手による毒殺説が流れている。著名な人物の死に際してありがちな情報だが、もしそれが万一本当であるなら、大変なことになるだろう。(2004/11/13)

|
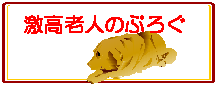
![]()
![]() メールはこちらまで。
メールはこちらまで。